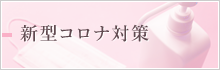12月診察スケジュール
| 2017年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
■木・日が休診日です。 土曜日は午前中診察
21日~24日まで連休です。 年末は29日まで診察予定ですが変更になることもあります。 年始は4日木曜日から仕事初めの予定です。
野牡丹
野牡丹に名だたる山の端霞みをり
[注・「やまのは」とは古語で、遠く望んだ山の、空に接する部分、 「名詞の霞(かすみ)は、三春の季語であるが、動詞の「かすむ」は季語ではない。]
この季節に鉢植えでよく見かける名前を知らない美しい花。 気にかかり調べてみると「野牡丹」でした。 名前の由来は牡丹のように大輪で美しいことから、(牡丹には似ていないようにも思えるけど) 原産地はブラジルで、夏から11月頃までの長い間咲きます。常緑樹。 色は紫の他、赤、白がありますが、紫のものをよく見かけます。
この紫いろのを【紫紺野牡丹】と言い しべは全て紫色 【ふつうの「野牡丹」】もあって、それは まんなかのしべの一部が黄色い ちなみに「しべ」というのは、 【蕊▼・蘂▼】花の生殖器官、ずいのこと。 と言うことは この写真は ふつうの「野牡丹」???? なかなか難しいですね。
写真・文 KISE
11月の診察スケジュール
| 2017年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
■が休診日です。
3日祝日は午前中診察予定 11日土曜日は学会の為休診させていただきます
柊
「柊の 葉の間より 花こぼれ」 高浜虚子  「柊」というと節分のイメージが強く、イワシの頭を刺した紙のお供えを思い出す。しかし柊の花は秋。ちょっと早いかもしれないが、十月の末ぐらいになると花が咲くのでお許し願おう。また同名の魚がいるが、これは少し別物。命名の由来などは知らない。ご存知ならばお教え願いたい。
「柊」というと節分のイメージが強く、イワシの頭を刺した紙のお供えを思い出す。しかし柊の花は秋。ちょっと早いかもしれないが、十月の末ぐらいになると花が咲くのでお許し願おう。また同名の魚がいるが、これは少し別物。命名の由来などは知らない。ご存知ならばお教え願いたい。
 木犀科。葉は固くてギザギザでさわると痛い。 それで、さわると疼(ひいら)く、ひりひり痛むところから「疼木」となる。 古くからその鋭いトゲによって邪気を払う木とされ、庭に植える習慣があった。鬼が目を突かれて退散したという伝説 、「鬼の目突(おにのめつき)」から、2月の節分には、柊の枝葉を戸口に立てて、その葉っぱのとんがりで鬼を追い払う。イワシの頭を柊の枝の先端に刺して、その匂いで鬼を退散させる。豆がらをたくさん巻き付けて、ガラガラ音を鳴らして鬼を退散させる。と言った厄除けの習慣が現在も残っている。 また、ネズミが通り抜けるようなところへ柊の枝葉を立てておくと、ネズミもトゲを恐れて通らなくなる、という効き目もあったらしい。 12月24日の誕生花(柊)花言葉は「先見の明」(柊)
木犀科。葉は固くてギザギザでさわると痛い。 それで、さわると疼(ひいら)く、ひりひり痛むところから「疼木」となる。 古くからその鋭いトゲによって邪気を払う木とされ、庭に植える習慣があった。鬼が目を突かれて退散したという伝説 、「鬼の目突(おにのめつき)」から、2月の節分には、柊の枝葉を戸口に立てて、その葉っぱのとんがりで鬼を追い払う。イワシの頭を柊の枝の先端に刺して、その匂いで鬼を退散させる。豆がらをたくさん巻き付けて、ガラガラ音を鳴らして鬼を退散させる。と言った厄除けの習慣が現在も残っている。 また、ネズミが通り抜けるようなところへ柊の枝葉を立てておくと、ネズミもトゲを恐れて通らなくなる、という効き目もあったらしい。 12月24日の誕生花(柊)花言葉は「先見の明」(柊)
写真と文 KISE
10月の診療カレンダー
| 2017年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
土曜日の診察は12時までです。
■が休診日です。
9日祝日は午前中診察予定
川崎医療福祉大学・大学院に行ってきました
夏の終わり今年で5年目の、 倉敷市川崎医療福祉大学・大学院に出前授業に行って参りました。 岡山県は助産師活動が活発な所で、実践も優れています。
院生、修了生とも課題を持って参加してくれ、授業が終われば揃って記念撮影。楽しい時間でした 
向上心溢れる若い助産師達、学生の熱気に押されて、私達も心地よい刺激を受けました。 まだまだ、気付かされる事多し!
クコ
枸杞
天候不順のせいかどうも体調が優れない。漢方に相談したらクコの花を処方されました。中国名で「枸杞」とかいて、日本では「くこ」というようです。

学名では Lycium chinense Lycium : クコ属 chinense : 中国の Lycium(リシウム)は、 中央アジアの Lycia という土地に生えていた、とげの多い木「lycion」の名前に由来しています。
夏から秋にかけて紫色の花が咲き、そのあとで赤い柔らかい実がなり食べられる。実の赤い色は、干してもなかなか色落ちしない。この実を酒や焼酎に漬けて「クコ酒」にします。ものの本によると、根の皮は解熱や強壮薬にもなる。
根は「地骨皮(じこっぴ)」 という漢方薬になる。 中国と日本では古くは「沼美久須利(ぬみくすり)」と呼ばれるなど薬として有名で、 栽培も盛んだったと書かれています。
枝にはとげあり、とげが多いところから生垣としても植えられる。
「枸杞子」は薬膳料理にもよく用いられているほか、中華料理のデザートなどにも使われることがあります。「枸杞子」は、さまざまな健康効果も期待できるうえ、美味しく、料理にも美しく映えるので、一石二鳥ならぬ、一石三鳥ですね。
 S.KISE 文章 写真
S.KISE 文章 写真
9月の診察スケジュールです。
| 2017年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が休診日です。
18日と23日の祝日は午前中診察予定
8月のお知らせ
薊の名前の由来は、「和名抄(わみょうしょう・932)」に「葉には刺(とげ)多し、阿佐美(あさみ)」という記述があります。また「植物名の由来(中村浩・1980)」には、「アザムという言葉は、アサマから転訛(てんか)したもので、傷むとか傷ましいの意である」という解説があります。アザミに触ると刺があり痛いので、アザム草が転訛してアザミと呼ばれるようになったということらしい。
ところが別の語言もある。沖縄の八重山地方では、とげを「あざ」と呼ぶことから「あざぎ」(とげの多い木)と呼ばれ、しだいに「あざみ」になった。
ホームページをリニューアル致しました。
この度、池上助産院のホームページをリニューアル致しました。今後とも宜しくお願い致します。